Copyright 2011 JCIB.CO. All rights reserved. No reproduction without written permission.
■ ウコンとは?
・ 人類に愛されてきたウコン
・ ウコンの歴史
・ 生活にとけ込むウコン
・ 注目されるウコンの成分
■ ウコン主成分クルクミンの課題
・ ウコン主成分クルクミンとは?
・ クルクミンの効用
・ 日本人の肝臓を守るクルクミン
・ クルクミンの可能性
・ クルクミンの課題
■ 新開発セラクルミンの登場
・ クルクミンの弱点を克服
・ 27倍の高吸収
・ 高い安全性
・ 沈殿しにくく、飲料にも使いやすい


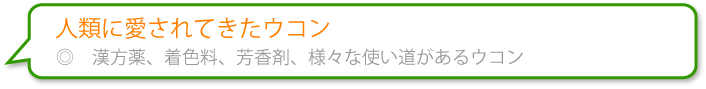
ウコンとは、南アジア、アジア、アフリカ、中南米の熱帯地域から亜熱帯地域にかけて生息するショウガ科の多年草植物です。使用する際には、まずこの根を水洗いして、皮をむき、煮込んだ後に天日で乾燥させます。そしてそれを細かく砕き、粉末状にしたものが粉ウコン。ターメリックと呼ばれるもので、我々に馴染みのあるウコンの姿です。
この粉ウコンはアキウコンの根からできます。それ以外にウコンと呼ばれるものに、ハルウコンやムラサキウコンがありますが、食用になるのは、アキウコン。それ以外は基本的に薬用・染料として使用されています。
食欲をそそる色は着色料として、そして複雑な風味をもつ芳香成分は香辛料として使われてきました。加えて、古来よりウコンはカラダに良いとして、漢方薬としても使用されています。まさに人類に愛されてきた植物といえます。



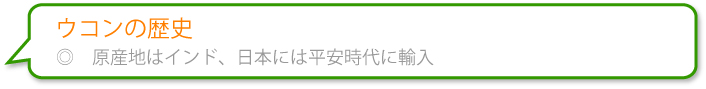
原産地はインド。歴史は古く、インド半島にアーリア系民族が定住し始めた紀元前2000年〜1500年頃には、すでに栽培され、利用が始まっていたという記録が残っています。
日本には、平安時代中期に中国から輸入されました。なお、中国では鬱金(うこん)の漢字からも推測できるように、鬱病の治療薬として使われています。
日本に渡ってきたウコンは、はじめに漢方薬として使われ、その後、染料、食料にと用途を広げていきました。栽培に置いては、本土では気温と湿度が足らずに困難なため、琉球王国(現・沖縄県)で室町時代に栽培されるようになったと言われています。沖縄県では現在も「うっちん」として栽培され、親しまれています。


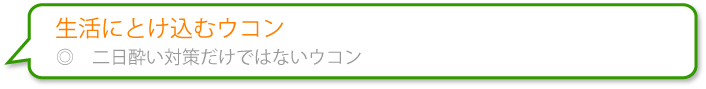
いまや悪酔い・二日酔い対策の強い味方として認知されているウコン。そこに含まれるクルクミンという色素成分には、胆汁の分泌を促し、肝臓の働きを活発にして、悪酔いを引き起こすアセトアルデヒドの代謝を促進する作用などが知られています。
悪酔い対策として、飲料やサプリメントなどで見る機会も多いと思いますが、ウコンは日本人の食生活にもとけ込んでいます。日本のカレーの消費量が、インド人に次いで世界第2位であるのは有名な話ですが、カレーの主要スパイスとして使われているのがこのウコン。そして、その鮮やかな色から、カレーと一緒に食べる福神漬けやたくわんの天然着色料としても使われています。これらの染料は食品だけでなく、化学薬品を使わない染料として、敏感肌の人に向けての衣類の染色剤としても使用されています。



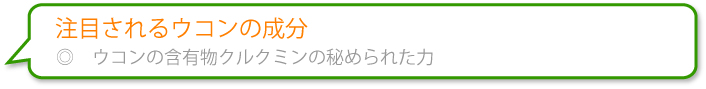
香辛料、着色料、漢方薬とあらゆるジャンルで使われる利便性の高いウコン。人間の生活と密接な関係を築いてきたこの植物ですが、近年はその含有物であるクルクミンが脚光を浴びています。
古来より漢方で信じられてきた肝機能を正常に戻す作用はもちろんのこと、心不全の予防や抗ガン作用、アルツハイマー病、パーキンソン病にも、クルクミンが効果を発揮することが明らかになりました。
また、その他にも、リウマチ、関節炎、筋肉疲労とさまざまな分野の治療薬としても注目を集め、研究は盛り上がりを迎えています。

参考:THE MOLECULAR TARGETS AND THERAPEUTICS USES OF CURCUMIN IN HEALTH AND DISEASE(一部引用改変)
クルクミンの応用分野
